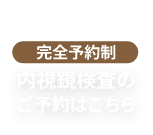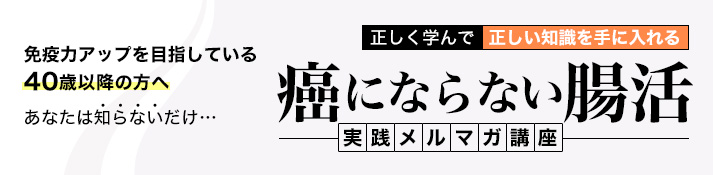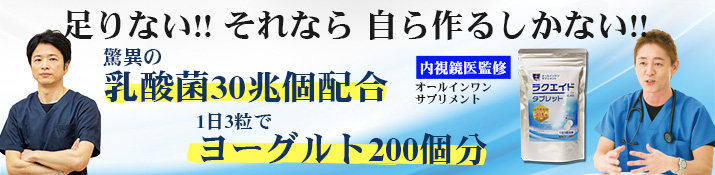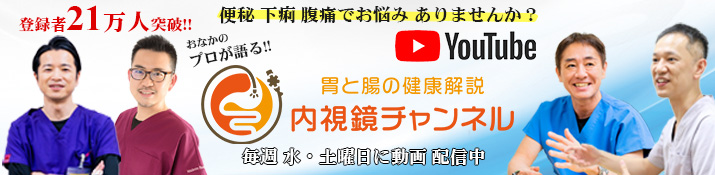MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

腸内フローラ検査で乳酸菌やビフィズス菌の割合は正確に分かるの?!
2025年05月26日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
ホノルルトライアスロンも無事に終わり、また来年のレースに向けて身体を作り直していこうかと考えているところです!
なかなかまとまった時間が取れない今日この頃ですが、
来年に向けての目標
1,週1回の筋トレを週2回に増やす!
2,1,2週間に1回は1時間でも良いのでバイクに乗って外走行
3,実際のレースと同じバイク40キロ走行の後にラン10キロを走る回数を増やす!
4,スイム1.5キロのタイムを速くする練習をする!
5,筋肉を増量して、体脂肪を少し落とす!
この5つを目標に掲げて、早速先週末からトレーニング再開しました!
腸内フローラ検査を受けている患者さんから
「乳酸菌やビフィズス菌のサプリメントを摂取しているのに、腸内フローラ検査で乳酸菌やビフィズス菌の割合があまり増えないかむしろ減った」
という質問を受けることがありますが、
外から摂った菌(プロバイオティクス)は定着しにくい
とされています。
ビフィズス菌や乳酸菌をサプリやヨーグルトなどで摂っても、
それらが腸内(特に大腸)に長期間住み着くこと(定着)は難しい
とされています。
多くは一過性に通過し、
腸内環境に変化を与えた後、
便として排泄されます。
そのため、
摂取をやめるとすぐにいなくなってしまうことも多く、
「摂っていても腸内の比率として定着するとは限らない」
可能性があります。
次に、
腸内フローラ検査の限界があります
現在の腸内フローラ検査(便を用いた解析)は、
大腸のごく一部の細菌の構成をスナップショット的に見るもの
です。
タイミングや便の採取状況、生活習慣、直前の食事などでも結果は左右されるため、
必ずしも腸内の全体像や機能的な改善が測れているとは限りません。
それと、
腸内の「土壌」が整っていないと菌は育たない
です。
例えるなら、
どんなに良い種(=菌)をまいても、土(=腸内環境)が痩せていれば育ちません。
腸内細菌が住み着くには、
「プレバイオティクス(菌のエサ)」
が不可欠です。
たとえば、
食物繊維やオリゴ糖、レジスタントスターチなどの摂取が不十分だったり、
腸内が炎症状態にあると、
せっかく摂った菌が活躍できない可能性があります。
さらには、
「リーキーガット(腸漏れ)」
があると、これは腸の粘膜バリアが弱くなり、本来入るはずのない物質が体内に漏れ出してしまう状態を指します。
これがあると、以下のようなことが起きやすくなります
★食事や菌に対する過敏な反応(アレルギー、炎症)
★慢性疲労、頭痛、肌荒れ、自己免疫の悪化など
★善玉菌が定着しにくく、腸内環境が不安定に
このような状態では、サプリメントを摂取しても効果が出にくいケースがあり、
まず腸のバリア機能(腸漏れ)を整えることが優先されます。

「乳酸菌やビフィズス菌サプリメントは腸内に定着しなくても意味があるのか?」
について簡単に説明します。
乳酸菌、ビフィズス菌のサプリメントは腸内に菌を定着させること以上に、
乳酸菌の場合は
1日1兆個の乳酸菌で小腸内の免疫活性化スイッチを押して、免疫を上げることにより腸内環境をよくすることが目的
です。
小腸での免疫を上げることによって、
★風邪や胃腸炎、コロナウィルスなどの感染症予防
★花粉症や喘息、アトピー性皮膚炎アレルギーの改善
★がんや様々な生活習慣病の予防
が期待されます。
ビフィズス菌や乳酸菌が腸内に定着しなくても、
摂取すること自体に複数の有益性
があります。
これは、まるで
「花壇にお花の種を蒔いて定着はしなかったけど、その種から出た香りやエネルギーが周囲の環境を整えてくれた」
ような働きです。
★有益性①:腸内環境の一時的な改善(通過菌としての効果)
ビフィズス菌や乳酸菌は、サプリや食品で摂取したあと、多くは数日で便とともに排出されます。
しかし、
この「通過」する過程
で、以下のような働きをしてくれます:
○乳酸や酢酸を作って腸内を酸性に保つ(これにより悪玉菌が増えにくい環境に)
○免疫細胞への刺激や調整効果(NK細胞の活性化、IgA分泌の促進など)
○炎症の抑制作用(腸粘膜への刺激を減らし、バリア機能を守る)
つまり、
「腸に住み着かなくても、通っていく間に良い働きをしてくれる」
わけです。
★有益性②:腸内細菌の代謝バランスをサポート
乳酸菌やビフィズス菌が作り出す代謝物、特に
「短鎖脂肪酸(酢酸・プロピオン酸・酪酸)」
には以下の効果があります
○大腸の細胞のエネルギー源となり、粘膜を修復
○腸のpHを下げて、悪玉菌の増殖を防止
○全身の炎症を抑え、メンタルや代謝にも良い影響
たとえ摂取したビフィズス菌自体が酪酸を作らなかったとしても、酢酸を出すことで他の酪酸菌の活動を助けるという「チームプレイ」があります。
★有益性③:免疫・アレルギーへの影響
最近の研究では、乳酸菌やビフィズス菌による腸管免疫の調整効果が注目されています。
○アトピー性皮膚炎の症状改善
○花粉症などのアレルギー反応の緩和
○自己免疫疾患の緩和の可能性(前臨床段階)
これらは
「菌がそこに住んでいるかどうか」よりも、
どれだけ“刺激”として腸内に届いているかが重要
です。
★有益性④:便通改善やガスの減少などの“症状緩和”
便秘、ガス、お腹のハリといった症状は、腸内での発酵バランスや腸の動きと密接に関係しています。
乳酸菌やビフィズス菌は
○便を柔らかくする働きのある短鎖脂肪酸を作る
○腸管の動きを刺激する
○他の善玉菌(酪酸菌など)を間接的に活性化する
といった経路で、症状そのものを軽減する効果があることもあります。
★★★患者さんへのわかりやすい一言まとめ★★★
「乳酸菌やビフィズス菌サプリは、“住み着かなくても”通っていくだけで、腸内で掃除・空気の入れ替え・免疫の応援団のような役割を果たしてくれます。
定着=効果ではありませんので、継続して意味がある場合が多いですよ。」
★★★食事による腸漏れ対策、腸内環境改善対策★★★
★プレバイオティクスの見直し
食物繊維(特に水溶性)、オリゴ糖、発酵食品など、
「菌のエサ」
となる食品の摂取を意識しましょう。
以下が効果的です
○水溶性食物繊維:昆布、わかめ、ごぼう、オクラ、モロヘイヤ
○レジスタントスターチ:冷ごはん、バナナ(特に青い状態)
○オリゴ糖:玉ねぎ、にんにく、アスパラガス、バナナ
★腸の炎症を抑える食生活
○グルテンやカゼイン、人工甘味料など、腸に刺激を与えやすい食品を一定期間避ける
○精製糖質・添加物・アルコールを控える
○EPA・DHAなどの抗炎症脂肪酸を積極的に摂る(青魚や亜麻仁油など)
では、今週も頑張っていきましょう!
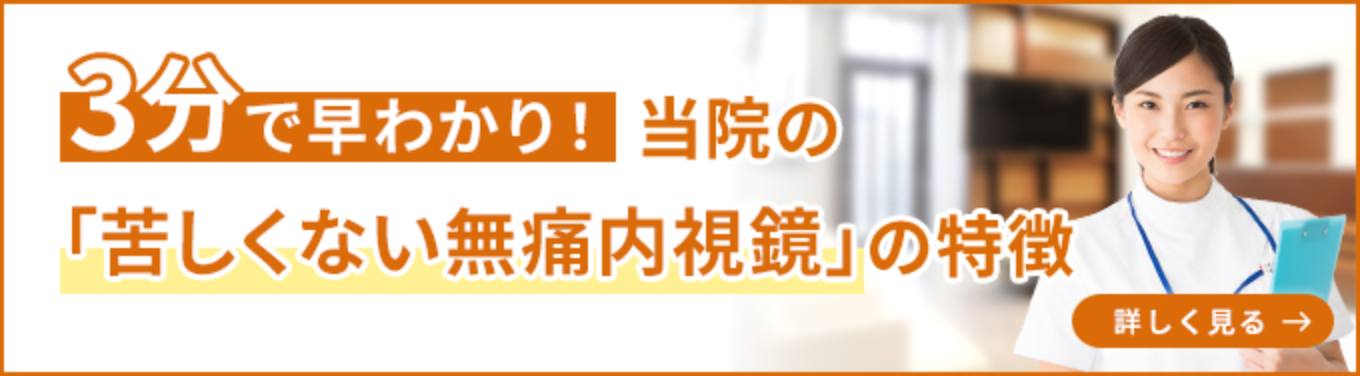
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。