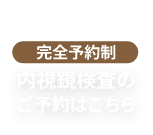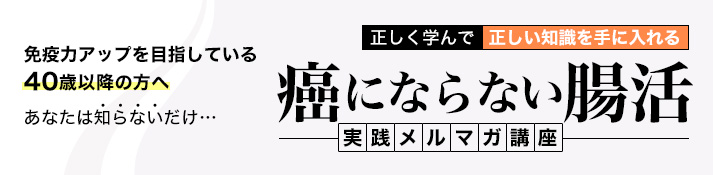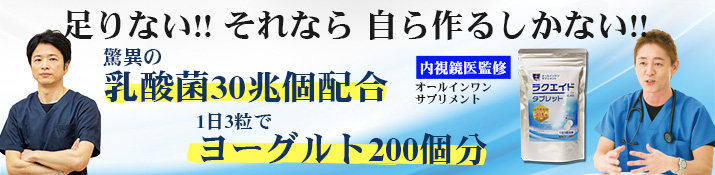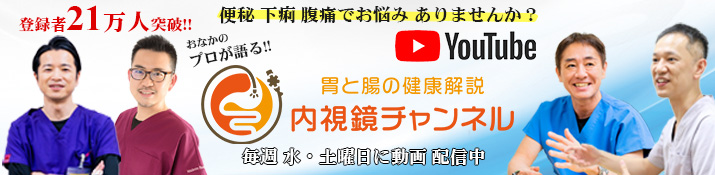MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

認知症と腸内環境、タンパク質の関係性!?
2025年06月30日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
先週始めから右肘の痛みがあり、週末にスポーツ整形外科受診しました。
レントゲンやエコー検査行ってもらいました。
診断名は予想通り
上腕骨外側上顆炎
通称
テニス肘
ですね。
いわゆる職業病ですね。
内視鏡検査のやり過ぎ
による腱の炎症です。
上腕骨外側上顆とは
肘の外側にある骨の出っ張りの部分(上腕骨の遠位端)で、この部位に付着する手首や指を伸ばす筋肉(伸筋群)の腱が、
繰り返しの使用による微小損傷・炎症
を起こす状態
が
この「テニス肘」です。
内視鏡検査をしないわけにはいかないので、湿布と炎症止め服用しながら改善を目指します!

さて、
認知症
気になる人多いですよね。
認知症は高齢化が進む現代社会において、大きな関心が寄せられている病気のひとつです。
一般には
「脳の病気」
と考えられがちですが、最近では
「腸とのつながり」
が注目されています。
そして、その腸の健康に欠かせない栄養素の一つが
「タンパク質」
です。
今回は、
「認知症」「腸内環境」「タンパク質」
がどのように関係しているのかを解説していきます。
■ 認知症の原因と進行メカニズム
認知症とは、
脳の神経細胞が徐々に壊れていき、記憶力や判断力、言語能力などが低下する疾患
です。
最も多いのは
「アルツハイマー型認知症」
で、
脳内にアミロイドβやタウたんぱくという異常なたんぱく質が蓄積することが原因
とされています。
これらの蓄積は、神経細胞の間の情報伝達を阻害し、炎症や酸化ストレスを引き起こし、最終的には神経細胞の死に至ります。
■ 腸と脳は「腸脳相関」でつながっている
ここで注目したいのが、
「腸脳相関(gut-brain axis)」
という考え方です。
これは腸と脳が双方向につながっており、互いに影響を与え合っているというものです。
腸には「腸内細菌」が約100兆個以上存在
し、
これらが生み出す代謝産物は、脳の炎症や神経伝達物質の生成にも関与していることが分かってきました。
腸内環境が悪化するとどうなる?
腸内の悪玉菌が優位になると、
有害物質(LPS:リポポリサッカライド)
が腸から漏れ出して、全身に炎症を引き起こすことがあります。
これが脳にも影響を与え、
「慢性炎症型の神経変性」
を加速させる要因のひとつと考えられています。
実際、アルツハイマー型認知症の患者さんでは、
腸内環境の多様性が低下していることが報告
されています。
■ タンパク質は腸と脳をつなぐ重要な鍵
タンパク質というと筋肉や皮膚の材料というイメージがありますが、脳や腸の健康維持にも不可欠です。
1. 腸粘膜の再生に必要
腸の内壁(腸粘膜)は2〜4日という非常に速いスピードで細胞が入れ替わっており、その再生には十分なタンパク質が必要です
タンパク質が不足すると、
腸のバリア機能が壊れて腸漏れ(リーキーガット)
が起きやすくなり、前述のように炎症物質が体内に漏れ出す原因になります。
2. 神経伝達物質の材料になる
タンパク質は、
脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミンなど)の材料となるアミノ酸
を供給します。
これらの物質は、感情のコントロールや集中力、記憶力などにも深く関わっており、
不足すると精神状態や認知機能に悪影響を与える可能性があります。
■ 認知症予防に役立つ食生活のヒント
認知症予防のためには、腸と脳の両方を整える食生活が重要です。
✅ タンパク質の摂取目安
-
1日 体重1kgあたり1.0〜1.5g
-
例:体重60kgの人なら60〜90g
卵、納豆、豆腐、魚、鶏肉、ヨーグルトなど
をバランス良く摂りましょう。
✅ 腸内環境を整える食品
-
発酵食品(味噌、納豆、キムチ、ヨーグルト)
-
食物繊維(ごぼう、海藻、きのこ)
-
プレバイオティクス(オリゴ糖、イヌリン)
これらを継続的に摂ることで腸内細菌叢が整い、炎症や有害物質の発生を抑えられます。
■ まとめ
認知症は決して「年齢のせい」だけではありません。
腸の健康状態や栄養状態と密接に関係しており、日々の食生活の積み重ねが予防につながる可能性があります。
腸を整えることは、脳を守ること。
そして、
タンパク質はその「土台」として最も重要な栄養素のひとつです。
「腸から考える認知症予防」、
ぜひ今日から意識してみてください
では、今週も頑張っていきましょう!
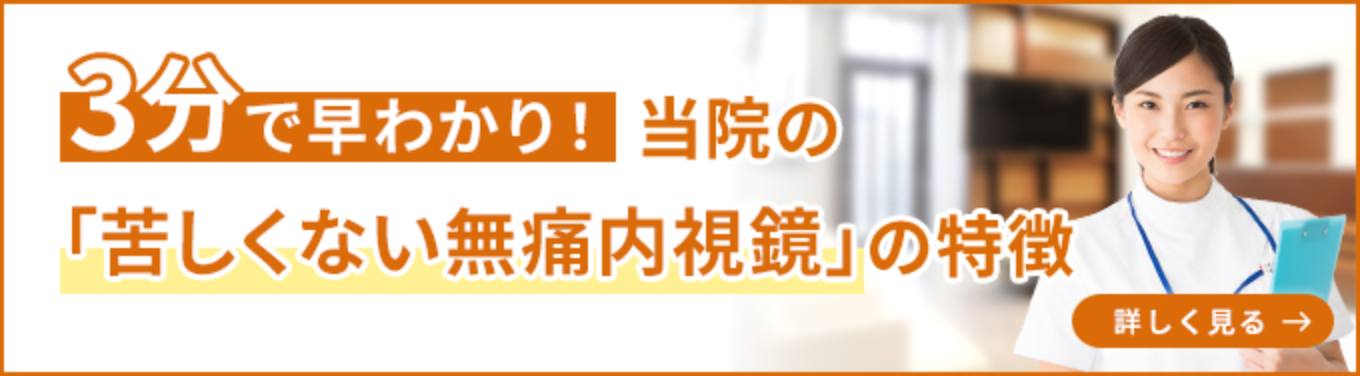
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。