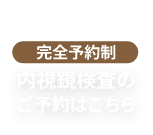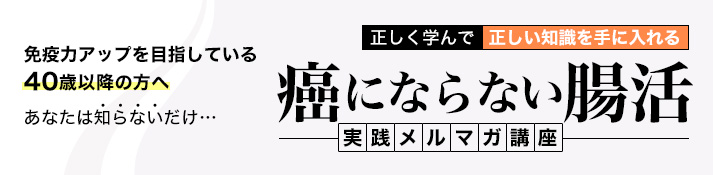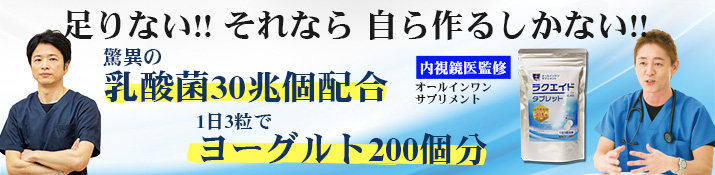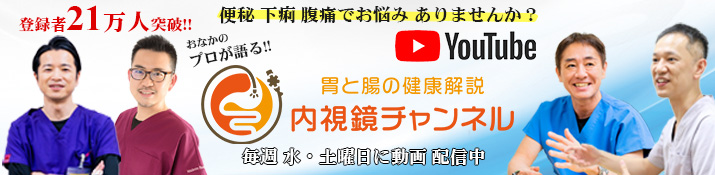MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

ビタミンDは腸活にも免疫力アップにも必須です!?
2025年07月14日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
オーソモレキュラーの栄養採血を定期的に受けています
が、
身体の栄養状態が詳細に分かるので、自分の体調管理や食事管理にとても役立っています。
身体の免疫力アップや腸漏れの改善に役立つ
ビタミンDの濃度
については特に気をつけて数値を注視するようにしています。
ビタミンD濃度は
2023年11月 53.3
2024年11月 56.1
2025年6月 62.7
と
目標である50以上はキープしています。
1日4000IUのビタミンDを服用していますが、
今回は
ビタミンD濃度を60以上にもっていきたかった
ので、
意図して
ビタミンDを1日5000IU
服用していました。
予想通り、ビタミンD濃度が60を越えました。
自分の身体の栄養素を自在にコントロールできるのはとても便利で体調管理に役立っています!

「ビタミンD」
といえば、
骨の健康や日光による生成が有名
ですが、
実はそれだけではありません。
近年の研究では、
腸のバリア機能を改善し、
「腸漏れ(リーキーガット)」
を防ぐ働きや、
全身の免疫細胞に直接働きかけて免疫力を高めるといった、多面的な作用が明らかになってきています。
今回は、
乳酸菌などとは異なるルートで、ビタミンDがどのようにして腸や免疫に影響を与えるのか、解説していきます。
腸漏れ(リーキーガット)とは?
腸漏れとは、
腸の粘膜バリアが壊れ、通常は吸収されない未消化のたんぱく質や毒素、細菌成分などが血中に漏れ出す状態を指します。
これにより、
慢性炎症や自己免疫疾患、アレルギー、皮膚トラブル
など多様な不調が起こると考えられています。
腸漏れの原因は、
ストレス、アルコール、添加物の多い食事、グルテンやカゼイン、そして栄養素の不足
などが挙げられます。
その中でも、
ビタミンDの欠乏
が注目されています。
ビタミンDが腸のバリア機能を高める理由
ビタミンDは、
腸管上皮に存在するタイトジャンクション(tight junction)と呼ばれる細胞間の「隙間を閉じる構造」に直接働きかけます。
このタイトジャンクションが緩むこと
で、
腸漏れが起こります。
ビタミンDは腸粘膜に存在する
ビタミンD受容体(VDR)
に結合し、
タイトジャンクションを強化する遺伝子の発現を促進します。
具体的には、
クローディン(Claudin)やオクルディン(Occludin)
といった密着結合タンパクの合成が活性化され、腸の「壁のつなぎ目」がしっかり閉じるようになるのです。
また、
ビタミンDは抗炎症作用
を持ち、
腸内での慢性炎症を抑えることで腸粘膜の修復も助けます。
ビタミンDは全身の免疫細胞に直接作用する
ビタミンDのもうひとつの重要な特徴は、
腸だけでなく、全身の臓器や免疫細胞に存在する「ビタミンD受容体(VDR)」に働きかけることです。
実は、
T細胞、B細胞、マクロファージ、樹状細胞など、ほとんどすべての免疫細胞にVDRが存在しています。
ビタミンDがVDRに結合すると、以下のような免疫調整が起こります。
-
自然免疫の強化:マクロファージが細菌やウイルスを貪食する力を高める。
-
抗菌ペプチド(カテリシジンなど)の産生促進:病原体の殺菌作用を持つ物質の産生を促す。
-
過剰な炎症の抑制:T細胞の暴走を抑え、自己免疫疾患や慢性炎症を予防。
-
バランスの取れた免疫反応:必要なときにだけ免疫が働く「免疫の選択性」が高まる。
これらの作用は、乳酸菌による腸内環境の改善とは別のルートで免疫を整える重要なメカニズムです。
乳酸菌で腸内環境を整えることで免疫の土台を作り、
乳酸菌が小腸での免疫活性化スイッチを押すことで免疫を上げて、
ビタミンDで「免疫細胞の司令塔」を直接サポートする
という、相互補完的な関係にあります。
現代人はビタミンD不足に陥りやすい
日照不足、日焼け止めの常用、屋内での生活スタイルの増加により、
現代人の多くは慢性的なビタミンD不足
に陥っています。
特に、
腸の不調やアレルギー、自己免疫疾患が気になる方は、
血中ビタミンD濃度(25(OH)D)を一度測定してみると良いですよ。
どれくらい摂ればよいか?
日本の推奨摂取量は
8.5μg(340 IU)/日
とされていますが、
これは欠乏を防ぐ最低限の量
であり、
免疫機能を高めるには
1日50〜100μg(2000〜4000 IU)
が望ましいとされています。
ビタミンDは魚(鮭、いわし)、卵黄、きのこ類に含まれていますが、
必要量をすべて食事でまかなうのは困難なため、1日4000IUのサプリメント、
特に
羊毛ではなく、藻類などの植物由来の原料で作られた高濃度のビタミンDサプリメント
がお勧めです。
では、今週も頑張っていきましょう!
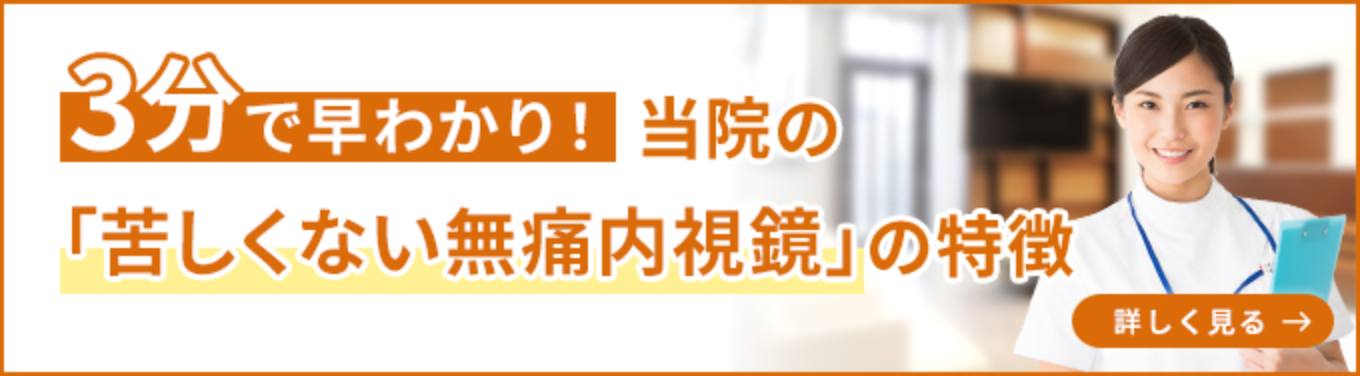
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。