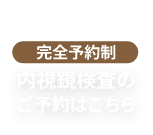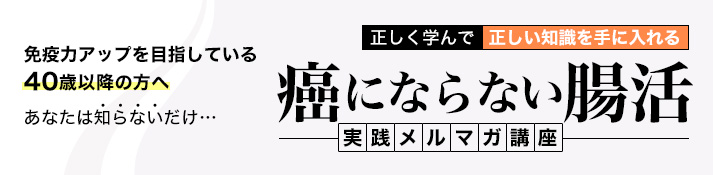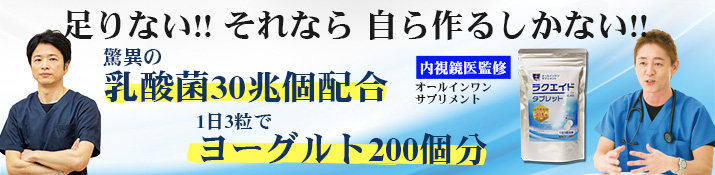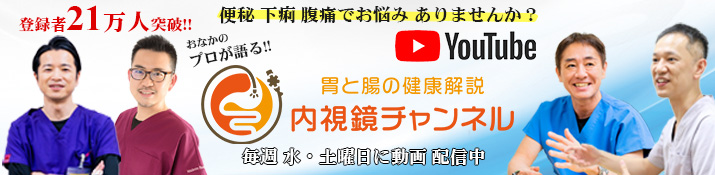MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

血糖値が下がらない本当の理由。カギは「腸漏れ」と「最強タッグ」にあった!?
2025年11月10日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
12月23日のクリスマス前に最新刊が
KADOKAWA出版
から発売されることになりました!
今回のテーマは
腸疲労
ということで、腸内環境と腸の疲労を関連させての書籍になります。
現在、頑張って書籍書いていますので、是非12月23日に手に取って頂けるとうれしく思います!
腸疲労
https://www.amazon.co.jp/dp/4046074736
「食事で糖質を控えているのに、HbA1c(ヘモグロビンA1c)がなかなか下がらない」
「食後にひどい眠気や倦怠感がある」
健康診断などで血糖値の高さを指摘され、このように悩んでいる方は非常に多いのではないでしょうか。
多くの方が
「糖尿病=糖質の摂りすぎ」
とだけ考えがちですが、
私たち消化器内科医は、日々内視鏡で腸を診ているからこそ、全く別の根本原因が隠れている可能性を強く感じています。
その最大の原因こそ、私たちが警鐘を鳴らし続けている
「腸漏れ(リーキーガット)」
です 。
今回は、
なぜ腸の状態が血糖値を左右するのか、そしてその対策の鍵となる
「食物繊維」
「ビタミンD 4000IU」
「乳酸菌 1兆個」
という最強の布陣について、専門医の視点から徹底的に解説します。

①:糖尿病の隠れた原因、「腸漏れ」と「慢性炎症」
まず、
「腸漏れ」
とは何か、簡単におさらいしましょう。
健康な腸の壁は、
細胞同士が
「タイトジャンクション」
で固く結合され、鉄壁のバリアを築いています 。
しかし、
食生活の乱れ(糖質過多、悪い油、小麦グルテンや乳製品のカゼインなど )、ストレス、
そして腸壁の材料となるタンパク質不足 などが原因で腸内環境が悪化すると、
このタイトジャンクション
が緩み、腸壁に無数の隙間ができてしまいます。
【なぜ腸が漏れると、血糖値が上がるのか?】
ここが最も重要なことです!
腸に穴が開くと、本来ならブロックされるはずの
悪玉菌の死骸(LPS:リポ多糖)や、未消化の食べ物といった「異物」
が、血中にダダ漏れになります 。
体はこれを「侵入者だ!」と認識し、免疫システムが作動。
全身で常に小さな
「慢性炎症」
の状態に陥ります 。
この
「炎症」
こそが、糖尿病の引き金です。
炎症によって体中から放出される炎症性サイトカインという物質が、
インスリン(血糖値を下げる唯一のホルモン)が働くための「鍵穴」を塞いでしまうのです。
その結果、
インスリンがいくらあっても効きにくい
「インスリン抵抗性」
という状態が完成します。
これが、2型糖尿病の根本的なメカニズムです。
つまり、血糖値が下がらない原因は、糖質の摂りすぎだけでなく、腸漏れによって引き起こされた「慢性炎症」にあるのです。
②:腸内細菌のエサ、「発酵性食物繊維」の真価
では、
どうすればこの負のスパイラルを断ち切れるのか。
まずは、腸内環境を整えることから始めなければなりません。
その主役が食物繊維です。
しかし、ただ食物繊維を摂れば良いわけではありません。
重要なのは、腸内細菌のエサとなる
「発酵性食物繊維」
を摂ることです 。
食物繊維の本当の役割は、便のカサを増やすことだけではありません。
その最大の目的は、腸内細菌(特に善玉菌)に「発酵」してもらい、私たち人間にとっての「宝物」を作り出してもらうことです 。
その宝物こそが
「短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)」
です 。
この短鎖脂肪酸は、
1,腸の粘膜細胞の主要なエネルギー源となり、腸のバリア機能(腸漏れ)を修復します 。
2,全身に作用し、インスリンの感受性を高め、血糖コントロールを助けます 。
つまり、
発酵性食物繊維(海藻、きのこ、大麦、玉ねぎ、冷やごはん など)を摂ることは、
腸内細菌に「天然のインスリン感受性改善薬」を作ってもらうこと
に他ならないのです。
③:腸活の「最強タッグ」が糖尿病を遠ざける
食物繊維という「エサ」を与えると同時に、腸の「壁」と「住人」そのものを強化する必要があります。
そこで登場するのが、私たちが一貫して推奨している「最強タッグ」です。
1. 腸の”壁”を物理的に修復する「ビタミンD 4000IU」
ビタミンDは、骨のビタミンではありません。
全身の細胞核に指令を出す
「ステロイドホルモン」
です 。
その最も重要な働きの一つが、腸の細胞にある受容体(VDR)に結合し、
腸壁のタイトジャンクションを強化する遺伝子のスイッチを入れること
です 。
ビタミンDは、
腸漏れの「慢性炎症」を鎮める免疫調整作用
と
腸の「壁」を物理的に修復する作用
の両方を持ち合わせています。
しかし、
最新の調査では
日本人の98%がビタミンD不足
です 。
骨粗鬆症予防の目安量(1日340IU) では、この腸壁修復やがん予防 といった効果は期待できません。
全身の免疫機能を最適化するためには、上限量である
1日4000IU(100μg)
の積極的な摂取が、現代人には不可欠なのです 。
2. 腸の”免疫”を叩き起こす「乳酸菌 1兆個」
次に、腸の「住人」です。
「毎日ヨーグルトを食べている」
という方は多いですが、その常識はもう古いかもしれません 。
ヨーグルト1個に含まれる乳酸菌は数十億個。
しかし、
腸内に約38兆個もいる細菌生態系から見れば、それは微々たる数です 。
近年の腸活のトレンドは
「ポストバイオティクス」
これは、
菌が生きているか死んでいるか(生菌・死菌)よりも、
「菌体成分」そのものに重要な意味がある
という考え方です 。
私たちが推奨する
「1日1兆個」
という圧倒的な「数」の乳酸菌(死菌でも可)を摂取する目的は、腸に定住させることではありません。
その目的は、
小腸にある体最大の免疫器官
「パイエル板」
を刺激することです 。
1兆個という大量の菌体成分がパイエル板の免疫スイッチを一斉に押すことで、
腸管免疫が活性化し、腸のバリア機能が強化されます。
この免疫の正常化こそが、
腸漏れが引き起こす
「慢性炎症」
を鎮め、
「インスリン抵抗性」
を改善する鍵なのです。
まとめ:血糖コントロールの答えは「腸」にある
血糖値やHbA1cが下がらずにお悩みの方は、糖質制限だけでなく、ご自身の「腸」に目を向けてみてください。
- **「腸漏れ」**が慢性炎症を引き起こし、インスリンの効きを悪くしている。
- 対策は、腸内細菌のエサとなる**「発酵性食物繊維」**を摂ること。
- そして、腸の**”壁”を修復する「ビタミンD 4000IU」と、腸の”免疫”を活性化する「乳酸菌 1兆個」**という最強タッグで、腸のバリア機能を根本から立て直すこと。
これが、私たち消化器内科医がたどり着いた、血糖コントロールの新しい常識です。ご自身の腸の状態が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください
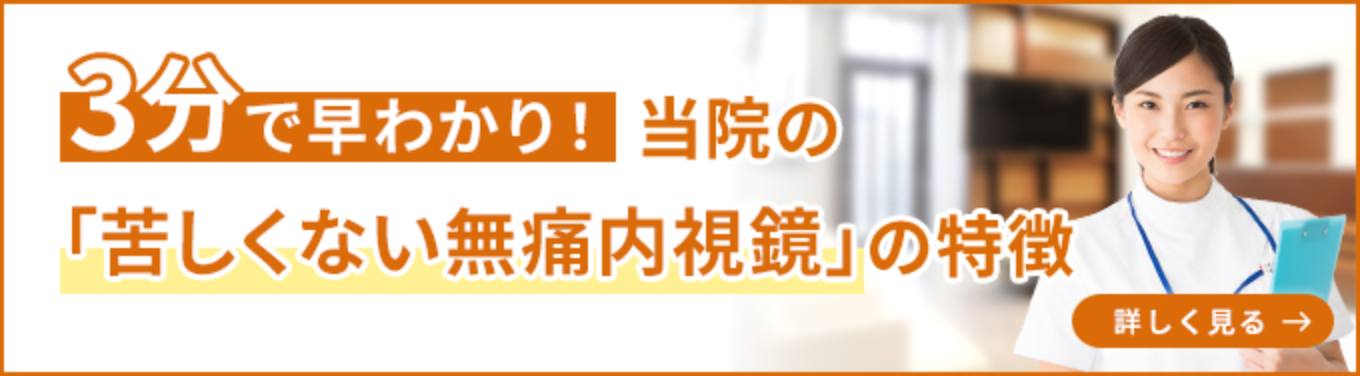
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。