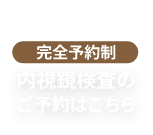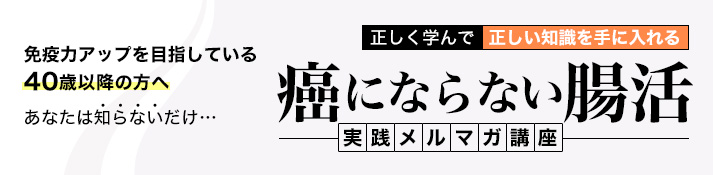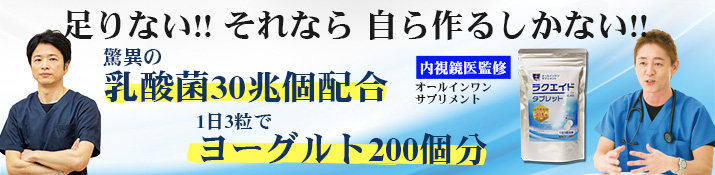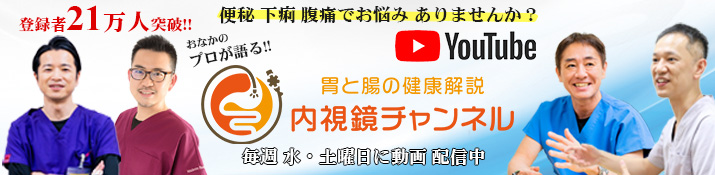MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

腸内環境は10日で変わる!認知症を防ぐ「最強の腸」の作り方!?
2025年11月17日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
日中は気温が高く、過ごしやすいですが、
朝晩は冷えており、寒暖差が激しく、体調を壊しやすい日々ですが、体調崩していないですか?
私は、年末に向けて運動のピッチを上げており、
来年2026年5月のホノルルトライアスロン2026に向けて
運動の機会を増やしています。
よく、診察室で
「認知症が心配です、何か予防方法などありますか?」
という質問をされることがあります。

現代の日本において、
寿命が延びる一方で、老後の最大の不安として
「認知症」
が挙げられます。
65歳以上の3.6人に1人
が認知機能に問題を抱えているとされ、軽度認知障害(MCI)を含めると患者数は
1000万人
を超えます。
認知症、特に最も多いアルツハイマー型認知症は脳の病気ですが、
近年、
その発症や改善の鍵が
「腸」
にあることが、研究の進展によって明らかになってきました。
腸は
「第二の脳」
とも呼ばれ、約1億個もの神経細胞を介して脳と密接に影響し合っています。
今回は、
なぜ腸の健康が脳の健康に直結するのか、
そして消化器病専門医としての知見も交え、認知症予防に効果的な
「最強の腸活術」
について詳しく解説します。
なぜ「腸の乱れ」が「脳の毒」になるのか?
アルツハイマー型認知症は、
脳内に
アミロイドβやタウタンパク質
といったタンパク質の塊がたまり、神経細胞を傷つけることで発症すると考えられています。
本来、
これらは脳を守る役割を果たしていますが、何らかの理由で脳から排出されずに蓄積すると毒性を持つようになります。
この排出プロセスを妨げる大きな要因が、
「腸内環境の悪化」
です。
腸内環境が悪化すると、
一部の悪玉菌の産生物が腸壁を傷つけ、粘膜に隙間ができる
「リーキーガット症候群(腸漏れ)」
を引き起こします。
この隙間からリポポリサッカライド(LPS)などの毒素が血中に入り込み、最終的に脳に影響して炎症を招きます。
通常、
有害物質は血液脳関門という強力なバリアでブロックされますが、
LPSは間接的に脳機能を変化させ、脳からアミロイドβなどを排出する経路を破壊してしまうのです。
結果として、脳内に毒性のタンパク質が滞留します。
さらに、
慢性的な便秘などで腸内環境が乱れると、悪玉菌がアンモニア、硫化水素、インドール、フェノールといった腐敗ガスを産生します。
これらの有害物質も血流に乗って脳に届き、
炎症を招いたり、神経機能を低下させたりすることが研究で明らかになっています。
認知症になりにくい「最強の腸」の持ち主の秘密
では、
認知症になりにくい腸とはどのような状態でしょうか。
重要なのは、
悪玉菌をできるだけ減らし、そのときどきで善玉にも悪玉にもなる
「日和見菌」と「ビフィズス菌」
をバランスよく豊富に持つことです。
2019年の研究では、認知症でない人の腸に日和見菌の一種である
「バクテロイデス」や「プレボテラ」
が多いことが判明しました。
特にバクテロイデスが多い人は、そうでない人に比べて認知症の罹患率が
約10分の1
になることも報告されています。
バクテロイデスは、
脳の健康維持に必須なビタミンB群の合成や亜鉛などのミネラルの吸収
に関与する可能性に加え、免疫抑制細胞である
「制御性T細胞」
を増やす働きがあります。
制御性T細胞は過剰な免疫反応を抑制し、炎症を抑えることで脳を認知症から守る役割を果たすのです。
また、
腸内細菌そのものだけでなく、腸内細菌の産生物も極めて重要です。
善玉菌(ビフィズス菌、酪酸菌、乳酸菌など)が作り出す
「酪酸」「プロピオン酸」などの短鎖脂肪酸や、そのもとになる「乳酸」
が特に注目されています。
高齢になっても認知症にならない人の腸には乳酸が多く、
乳酸は細胞のエネルギー源となり、アンモニアなどの有害物質から脳神経を保護する働きがあります。
短鎖脂肪酸の中でも研究が進む酪酸は、セロトニンの産生を助け、
さらには傷ついた脳神経の再生を促す脳由来神経栄養因子(BDNF)を増やす効果も期待されています。
腸内環境を整え、短鎖脂肪酸が増えることで、脳神経は傷つきにくく、再生しやすくなるのです。
10日で変わる!具体的な「腸活食事術」と最強の組み合わせ
朗報として、
腸内環境は決して固定されたものではなく、食生活を意識して10日ほど続けることで菌が入れ替わり、定着すると言われています。
まず、
悪玉菌を増やし腸内細菌叢のバランスを崩す可能性がある、
ソーセージやハム、インスタント食品などの「超加工食品」は避けるべきです。
その上で、
「善玉菌(プロバイオティクス)+善玉菌のえさ(プレバイオティクス)」
の組み合わせを意識しましょう。
- 善玉菌のえさ(食物繊維)を確保する:
◦ 食物繊維は便秘解消だけでなく、善玉菌のえさとなります。
◦ 野菜だけでなく海藻類も食べ、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維を2:1の割合で摂ることが理想です。
◦ 緑黄色野菜に豊富なファイトケミカル(ごぼうのアルクチゲニン、赤しそのロスマリン酸など)は、
細胞の酸化を防ぎ、認知機能を維持する作用が期待できます。
◦ 腸内で水溶性食物繊維と同様に働く難消化性でんぷんが豊富な青いバナナや冷やご飯もおすすめです。
- 善玉菌+えさの組み合わせ:
◦ ヨーグルト+はちみつ。
◦ 納豆+キムチ。
◦ 大豆製品などの植物由来食品や、オメガ3系脂肪酸(サーモン、いわし、さば、うなぎ)も高い抗酸化作用を持ちます。
◦ これらの食材をバランスよく含む和食は、認知症予防の腸活として非常に優れています。
脳を守る「最強タッグ」:コーヒーとビタミンD・乳酸菌
通常の腸活食材に加え、「コーヒー」と「ビタミンD」をプラスすることで、認知症予防効果がさらに高まります。
○コーヒーの力: カフェインやポリフェノールには、神経を保護したり、血流を良くしたりする働きがあります。
さらに、小腸でGLP-1というホルモンを増やし、肝臓に届くとBDNFの分泌が促され、脳神経の再生をサポートします。
○ビタミンD: ビタミンDは、腸のバリア機能を高めるために積極的に摂取すべき成分です。
ビタミンDは単なるビタミンではなく、
体内ではホルモンのように働き、ビタミンD受容体(VDR)は体中のほぼすべての細胞(免疫細胞、腸管、脳など)に存在しています。
腸管においては、
VDRがカルシウム吸収を助けるとともに、腸粘膜の細胞の隙間を埋めて「腸漏れ」を防ぎ、バリア機能を維持します。
また、
神経保護作用を持ち、認知症予防につながる可能性も示唆されています。
ビタミンDは全身の免疫システムの「司令塔」として、病原体を排除し、炎症を抑える重要な役割を担っています。
○乳酸菌(プロバイオティクス):
ビタミンDが全身の司令塔なら、乳酸菌は「腸の免疫スイッチを押すトレーナー」です。
小腸には免疫細胞のトレーニングセンターであるパイエル板があり、
乳酸菌がこれを刺激することで腸管免疫(GALT)を活性化します。
乳酸菌は善玉菌を増やし、短鎖脂肪酸の生成を促進し、
腸のバリア機能を強化します。
腸の免疫を鍛えるためには、最低でも1日1兆個の乳酸菌を摂取することが極めて重要であり、生きた菌でなくても、
数が多い死菌でも効果があることが分かっています。
ビタミンDが免疫細胞のパフォーマンスを最大化し、
乳酸菌が腸内フローラを整え、免疫がスムーズに働く環境を作ることで、
これら二つは異なるアプローチながらお互いを補完し合う最強のタッグとなります。
腸と脳を整える生活習慣
食事だけでなく、自律神経を通じて腸の消化やぜん動運動を管理している運動や睡眠も重要です。
適度な運動や良質な睡眠は、腸のバリア機能や善玉菌の働きを高める助けになります。
○運動: ウオーキング程度の適度な運動で十分です。腸が刺激され血流が改善しますので、毎日歩くことをおすすめします。
○睡眠: 夕食は就寝の3時間前まで、入浴は1~2時間前まで(39~40℃のぬるめのお湯に15分程度)に済ませましょう。
脳を覚醒させないよう、就寝1時間前はスマホやパソコンを見ないことも大切です。
○血流改善: 脳の血流を改善し自律神経を整えるために、ガムを噛むことも推奨されています。
今日のあなたの腸を整える努力が、10年後、20年後の元気な脳を守ることにつながります。
腸活は、未来の自分への最高の投資なのです。
【認知症予防のための腸活まとめ】
腸活は、まるで精密な化学工場を管理するようなものです。
良質な原材料(食物繊維、発酵食品)を投入し、適切な触媒(ビタミンDや乳酸菌)を使うことで、
有害物質の排出を抑え(リーキーガット予防)、脳を守る有効成分(短鎖脂肪酸、BDNF)
を大量に生成する。
この工場(腸)の稼働状態が、私たちの人生の後半戦の「脳のパフォーマンス」を大きく左右するのです。
では、今週も頑張っていきましょう!
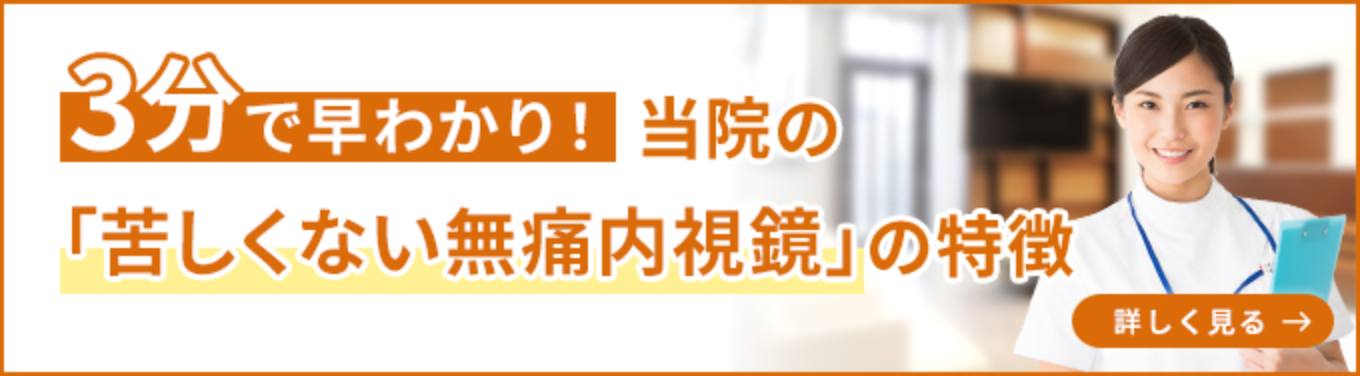
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。