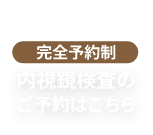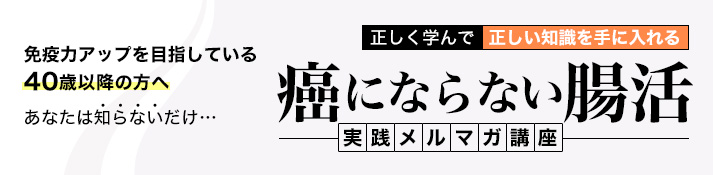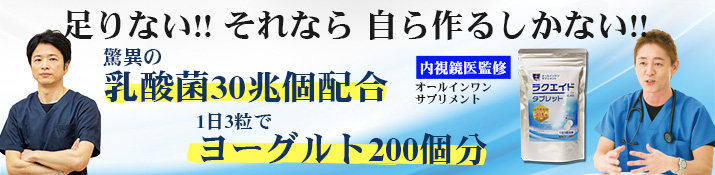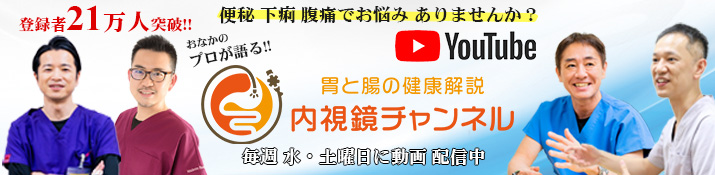MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

大腸がんが日本で激増している本当の理由!?
2025年11月24日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
だいぶ朝晩が寒くなってきて、朝ランがかなり快適になってきました!
ホノルルトライアスロン2026まで6ヶ月を切りましたので、
本格的に練習をやっていこうと決意しております。
正月休みは、時間がないとできないバイクの練習を本格的にしようかなと考えています。

診療をしていると、
大腸ポリープ、大腸がんが増えているなと実感します。
「大腸がんと食生活の密接な関連」
について、解説していきます。
現在、
大腸がんは、男女合わせた罹患数(かかる人数の多さ)で堂々の第1位です。
さらに、
死亡数においても、
女性は第1位、男性も第2位
と、増加傾向にあります。
わずか数十年前まで、日本のがんの主流は
「胃がん」
でした。
しかし、
戦後の急激な食生活の「欧米化」
に伴い、
この大腸がんが爆発的に増加しました。
この明確な統計の変動こそが、
大腸がんが「食源病」
としての側面を強く持つことを示しています。
肉と脂肪が作り出す「発がん物質」
なぜ、欧米型の食事が大腸がんのリスクを高めるのでしょうか?
鍵を握るのは、
高脂肪食と胆汁酸
です。
脂質の多い食事を摂ると、肝臓は消化を助けるために大量の胆汁を分泌します。
この胆汁の成分である一次胆汁酸は、通常は腸で再吸収されますが、
高脂肪食を常食していると、腸内の悪玉菌によって分解され、
二次胆汁酸
という物質に変化します。
この二次胆汁酸こそが問題なのです。
これは
大腸の粘膜を刺激し、遺伝子に傷をつける「発がん促進作用」
を持つことが知られています。
私たちは普段、大腸がんの原因として「赤身肉」の発がん性を気にしがちですが、
実際には、
その肉の脂を消化するために使われた胆汁が、腸内細菌の働きで毒物に変化する
という、複雑なメカニズムが背後にあるのです。
食物繊維の不足が「暴露時間」を伸ばす
もう一つ、食生活の欧米化で決定的に不足しているのが
食物繊維
です。
食物繊維は、二次胆汁酸などの毒素を吸着し、便の量を増やして排出を促す
「大腸のお掃除役」
です。
食物繊維が不足すると、
腸内通過時間(トランジットタイム)が長期化
します。
便が腸内にとどまる時間が長くなればなるほど、
発がん性の二次胆汁酸や腐敗産物に大腸粘膜がさらされる時間(暴露時間)が伸びてしまう
のです。
毒素にさらされ、慢性的な炎症が起こることで、良性ポリープからがんへと進行するリスクが高まる。
これが大腸がん発生の典型的なルートです。
専門医が推奨する「腸をがんにしない」食の二原則
では、私たちは何をすべきでしょうか?
大切なのは、単に「肉を我慢する」ことではなく、腸内環境のバランスを取り戻すことです。
1. 毒素を「無毒化」する腸内環境を育てる
善玉菌は、食物繊維をエサに短鎖脂肪酸を作り出します。
この短鎖脂肪酸は、
大腸のエネルギー源となり、炎症を抑え、がん細胞の増殖を抑制する作用
を持つ、
まさに
「天然の抗がん物質」
です。
穀類、海藻、きのこ、野菜
などの水溶性・不溶性両方の食物繊維を積極的に摂り、善玉菌のエサを供給し続けましょう。
納豆や味噌などの発酵食品も有効です。
2. 「脂質の量と質」を見直す
完全に脂質を断つ必要はありませんが、特に加工肉や牛肉・豚肉などの赤身肉の過剰摂取は控えるべきです。
週に一度のステーキを、魚(特にオメガ3脂肪酸が豊富な青魚)や鶏むね肉などに置き換える
など、脂質の「質」と「量」を意識的に調整しましょう。
大腸がんの増加は、現代の日本人の食生活が、私たちの腸の生理的な限界を超えてしまっている証拠です。
日々の食事を見直すことが、最も確実な予防策と言えるでしょう。
そして何より、早期発見に勝るものはありません。
40歳を過ぎたら、一度は大腸内視鏡検査を受けることを強くお勧めします。
では、今週も頑張っていきましょう!
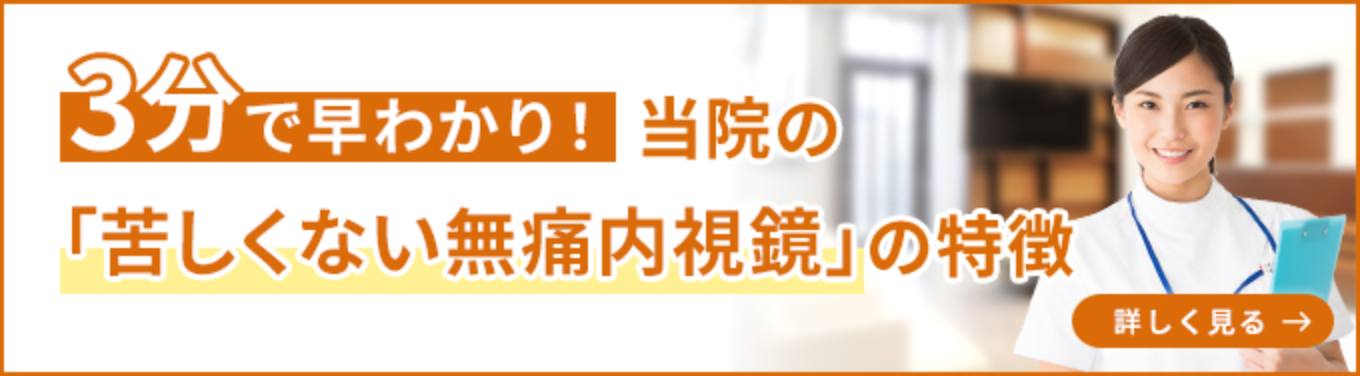
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。