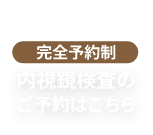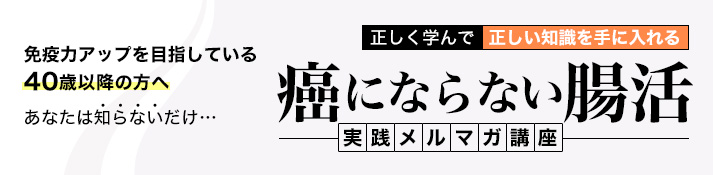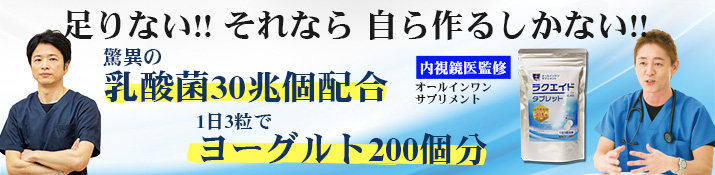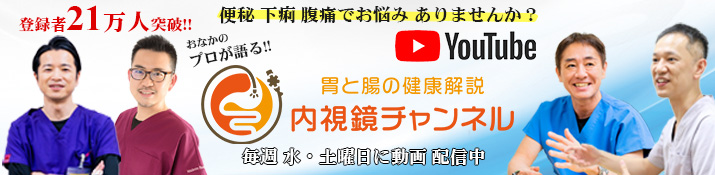MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

その油、腸と血管を壊します!病気を防ぎ、腸活にとって「正しい油」の選び方と使い方
2025年11月03日
- 院長ブログ
こんにちは、平島です。
空気の乾燥が強くなってきましたね。
喉の乾燥による声がれには
水分補給も重要ですが、のど飴も大切ですね。
私も乾燥すると声がかれてくる体質なので、
愛用する声がれののど飴があります。
カイゲンの羅漢果入り黒のど飴
です。
空気の乾燥による声がれに特に効果がある印象です。
しゃべるのが仕事の人は声がれは辛いと思いますが、こののど飴効果的ですので、是非試してみてください。
本日は、皆さんが普段から調理などに使っている
「油」
について解説していこうと思います。
「健康のために油を控えている」
「体に良いと聞いて、とりあえずオリーブオイルを使っている」
油に関しては、様々な情報が飛び交い、結局どうすれば良いか迷っている方も多いのではないでしょうか。
私たち消化器内科医は、日々多くの患者さんの腸を内視鏡で見ていますが、
「摂取する油の質」が、腸の健康状態、ひいては全身の不調に直結している
ことを痛感しています。
私たちの体を構成する約37兆個の細胞、その一つ一つを包む「細胞膜」の主成分は脂質です。
摂取する油の種類によって、この細胞膜の質が決まります。しかし、油の種類と使い方を間違えると、
アレルギー、糖尿病、がん、そして認知症といった現代病の多くに関わる
「慢性炎症」
の最大の火種となり得ます。
特に、
私たちが警鐘を鳴らす
「腸漏れ(リーキーガット)」
とも、油は密接に関わっているのです。

腸活のために
今すぐ見直すべき「悪い油」
と
積極的に摂るべき「良い油」
について、その戦略的な使い分けを徹底解説します。
①:今すぐ捨てるべき「悪い油」とその理由
家庭のキッチン、特に流し台の下に、大きな透明なペットボトルに入った
「サラダ油」
や
「キャノーラ油」
を常備していないでしょうか。
結論から言いますと、これらは調理油のスタメンから外し、使用を最小限にすることを強く推奨します。
これらの油の主成分は
「オメガ6脂肪酸」
です。
オメガ6自体は必須脂肪酸ですが、現代の食生活(加工食品、外食、揚げ物)では、その摂取量が圧倒的に過剰になっています。
【なぜオメガ6が問題なのか?】
オメガ6脂肪酸は、体内で
「アラキドン酸」
という物質に変わり、これが炎症を促進するシグナルを出します。
適度な炎症は体を守るために必要ですが、オメガ6が過剰になると、
体中で常に小さな「火だね」がくすぶっているような状態(慢性炎症)になります。
この慢性炎症が、腸の粘膜細胞に絶え間ないダメージを与え、
細胞同士の固い結合(タイトジャンクション)を緩めてしまうのです。
これが、
私たちが最も恐れる
「腸漏れ(リーキーガット)」
の最大の原因の一つです。
腸のバリアが壊れれば、未消化物や毒素が体内に侵入し、さらに全身の炎症を悪化させます。
天ぷらや揚げ物などでこの油を大量に使うことは、体に炎症の爆弾を投げ込んでいるようなものです。
もし使うとしても、風味付けの「ごま油」を少量垂らす程度にとどめ、加熱用の主役から降ろすべきです。
②:腸を守る「良い油」の戦略的使い分け
では、
何を代わりに使えば良いのでしょうか。
良い油は、
「①生食用(抗炎症)」
「②加熱調理用」
「③機能性(エネルギー)」
の3つに分けて戦略的に使い分けるのが鉄則です。
1. 生食用:腸の炎症を鎮める「飲む抗炎症薬」(オメガ3)
腸漏れの原因である炎症を鎮めるには、オメガ6とは真逆の作用を持つ
オメガ3脂肪酸(アマニ油、エゴマ油、青魚の油)
が不可欠です。
オメガ3は、
体内でEPAやDHAに変わり、
オメガ6による炎症促進プロセスをブロックし、体内の炎症を鎮静化させます。
まさに「飲む抗炎症薬」です。
【重要】
オメガ3は極めて熱に弱く、加熱すると瞬時に酸化して有害な物質に変わります。
絶対に加熱調理には使わないでください!
サラダや納豆、味噌汁にかけるなど、必ず「生」で摂りましょう。
光や空気でも酸化するため、遮光瓶に入ったものを選び、開封後は冷蔵庫で保管すること
が鉄則です。
2. 加熱調理用:熱に強い優等生(オメガ9・飽和脂肪酸)
では、
炒め物やソテーには何を使えばよいか。
答えは「熱に強い油」です。
○オメガ9脂肪酸(オリーブオイル):
不飽和脂肪酸の中では比較的熱に強く、酸化しにくい特性があります。
悪玉(LDL)コレステロールを下げる働きも期待できます。
加熱用には、抗酸化物質(ポリフェノール)が豊富な
エキストラバージンオリーブオイル
を選ぶのがベストです。
○飽和脂肪酸(バター、ココナッツオイル):
分子構造が安定しており、熱に非常に強い油です。オメガ6のサラダ油で調理するより、よほど健康的と言えます。
3. 機能性:最速のエネルギー源(MCTオイル)
近年注目されているのが
MCTオイル(中鎖脂肪酸)
です。
通常の油と異なり、MCTオイルは小腸で吸収されるとリンパ管を通らず、直接肝臓に運ばれ、即座に
「ケトン体」
というエネルギー源に分解されます。
一般的な油の約4倍も速くエネルギーに変わり、
脂肪として蓄積されにくいのが最大の特徴です。
また、
ケトン体はブドウ糖の代わりに脳のエネルギーになるため、認知機能のサポートとしても注目されています。
これも加熱せず、コーヒーや豆乳ヨーグルトなどに小さじ1杯程度かけて摂るのがおすすめです。
③:腸のバリアを根本改善する「最強タッグ」戦略
腸漏れを根本から改善するためには、これらの良質な油に加えて、私たちが常々推奨している
「ビタミンD」と「乳酸菌」
を組み合わせた「三位一体」のアプローチが鍵となります。
○良い油は、ビタミンD吸収の「最高の相方」
ビタミンDは脂溶性ビタミンです。1日4000IUという高用量のビタミンDサプリメントを飲んでも、良質な油(オメガ3やMCTオイル)と一緒でなければ、腸からの吸収効率が減ってしまいます。
○三位一体の連携
1,オメガ3(油): 腸の炎症そのものを鎮めます。
2,ビタミンD(4000IU): 腸の細胞核に働きかけ、壊れたバリア(タイトジャンクション)の修復・強化を促します。
3,乳酸菌(1兆個): 腸内環境という”土壌”を整え、善玉菌が産生する短鎖脂肪酸によってバリア機能を内側から支えます。
この三つの要素が揃って初めて、腸の健康は根本的に改善へと向かうのです。
日々の調理油を見直し、炎症を引き起こす油(オメガ6)から、炎症を抑える油(オメガ3・オメガ9)へと切り替えること。
それが、健康な腸を取り戻すための、最も効果的で確実な第一歩です。
では、今週も頑張っていきましょう!
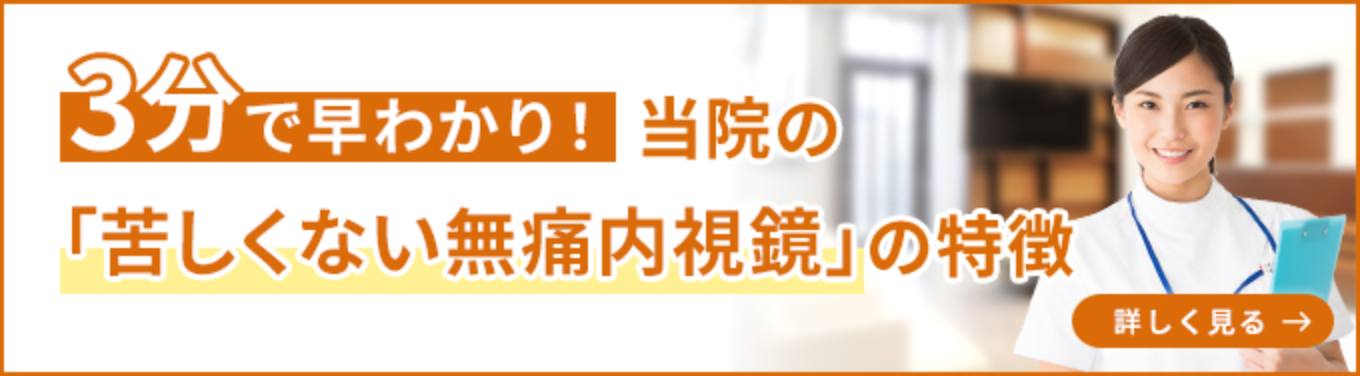
この記事を書いた人

平島 徹朗
医師
国立佐賀大学医学部 卒業。 大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部など、 多くの病院・内視鏡専門クリニックで消化器内視鏡診断・治療を習得後、2011年たまプラーザ南口胃腸内科クリニック開院。