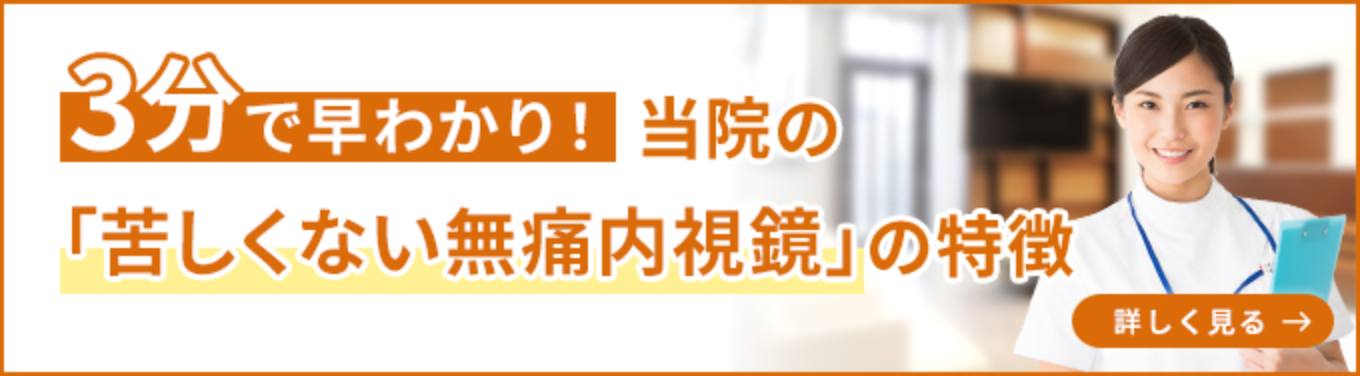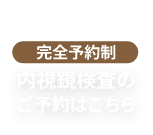MENU
閉じる
おすすめ内視鏡豆知識
Endoscopist Doctor's Knowledge

ヘリコバクター・ピロリ菌に関するよくある質問
ヘリコバクター・ピロリ菌とは?
ピロリ菌は1982年 にオーストラリアのロビン・ウォレンとバリー・マーシャルにより発見されました。約3×0.5μmの大きさのらせん状をした細菌で、4~8本のしっぽがあります。このしっぽをヘリコプターのように回転させて移動し、胃の前庭部(pylorus)に生息することから、ヘリコバクター・ピロリと名付けられました。
慢性胃炎の原因ですか?
ピロリ菌の発見以前はストレスや生活習慣が胃潰瘍の主な原因だと考えられていました。誰も日常的に起こる胃炎や胃潰瘍の原因が、細菌感染症だとは考えていなかったのです。研究者のほとんどが、胃粘膜のような酸性環境で生きられる細菌なんているはずがないという思い込みも存在していました。ウォレンとマーシャルによりピロリ菌が酸性環境で生きられるのは、ウレアーゼという酵素をつくりだしてアンモニアを産生し、胃酸を中和するからだとわかっています。
胃がんの原因ですか?
ピロリ菌が胃に感染するとピロリ菌から胃の粘膜に病原性タンパク質Cag A(キャグA)が注入され、慢性活動性胃炎と呼ばれる持続的な炎症を引き起こし、次第に胃粘膜が萎縮(胃粘膜が薄くなる現象)していきます。胃粘膜の萎縮とは言い換えると「胃の老化現象」のことで、胃酸の分泌が減少していき、消化不良や胃の不快感などの症状が出現してきます。
一度ピロリ菌に感染すると、年齢とともに胃粘膜の萎縮(胃の老化)が次第に進んでいき、強い胃粘膜の炎症が持続して、胃がんの発生リスク(ピロリ菌未感染者の約10倍以上)がより高くなることが判明しています。
ピロリ菌の感染者は、全くピロリ菌に感染したことがない人に比べて胃がんのリスクは10倍以上であることが報告されています。ピロリ菌に感染しているからといって、必ず胃がんになるとは限りませんが、胃がんを発症する人の99%がピロリ菌感染者だというデータがありますので、注意が必要です。
胃がんABCリスク検診とは?
2015年にヘリコバクター・ピロリ菌の除菌が、ピロリ菌の感染だけで保険適応になりました。それ以降、ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌が盛んにおこなわれるようになりましたが、そこには胃がんABCリスク検診の普及も関与しています。
自治体などが行っている胃がんABCリスク 検診とは、血液検査にてヘリコバクター・ピロリIgG 抗体検査(採血)でピロリ菌感染の有無を、ペプシノゲン(PG)検査(こちらも採血)で胃粘膜の炎症の程度を調べ、その結果を組み合わせて胃がんのリスクをA、B、C、Dの4群に分類して評価する検診です。
A群は抗体陰性、PG法陰性で、ピロリ菌に感染していないので抗体が作られていない状態で、胃炎も起こっていない状況です。B群は抗体陽性、PG法陰性でピロリ菌の感染が成立し、体内でピロリ菌に対する抗体が作られている状況ですが、まだ胃炎の程度が軽度のためペプシノゲン法が陰性の状態です。C群は抗体陽性、PG法陽性でピロリ菌の感染が成立し、体内でピロリ菌に対する抗体が作られている状況で、なおかつ胃炎がかなり進行している状態となりペプシノゲン法が陽性になった状態です。D群は、抗体陰性、PG法陰性の状態です。この状態はピロリ菌の感染が成立し抗体が作られていたのですが、胃炎が胃の中で完成していて、胃の中でピロリ菌が住み着ける環境がなくなり自然消滅してしまい抗体産生が行われなくなった結果です。そのため抗体は陽性から陰性に変化しますが、ペプシノゲン法は胃炎が進行している状態のため陽性のままなのです。
胃がんとは?
ヘリコバクター・ピロリ菌によって引き起こされる疾患の代表格と考えてよい胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、遺伝子のトラブルによりでがん細胞になることから始まります。がん細胞が発生し、体内の免疫システムから見つからないようにして無秩序に増えていくことにより大きくなっていきます。
がんが大きくなるにしたがい、徐々に粘膜下層、固有筋層、漿膜へと元の場所から徐々に大きくなるように、また粘膜の下側に向かって深く進んでいきます。胃がんが増大しより深く進むと、粘膜下層にある血管やリンパ管を介してがん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って、胃から飛び出して全身に広がります。血液の流れに乗って胃から離れた臓器で胃がん細胞がふえることを転移(てんい)と言い、肝臓や肺に転移が良くみられます。
また、特殊な胃がんとして、胃壁の中を硬く厚くさせながら広がり粘膜の表面にはあまり現れないタイプがあり、これをスキルス胃がんといいます。胃の漿膜の外側を越えて、お腹の中にがん細胞が散らばる腹膜播種(ふくまくはしゅ)が起こることがあります。リンパ管に沿って胃周囲のリンパ節転移が起こり、さらに遠くまでに広がると大動脈周囲のリンパ節まで腫れる事があります。胃以外の臓器に転移が認められた場合を遠隔転移と呼びます。進行度により治療方法が大きく異なり、早期に発見されればされるほど治癒が期待できます。
除菌すれば胃がんになりませんか?
ヘリコバクター・ピロリ菌を除菌することで、胃がんのリスクは約30~40%程度低下しますが、胃がんになるリスクが全くなくなるわけではありません。ピロリ菌により胃に慢性的な炎症が起こり胃の粘膜が薄くなる「萎縮性胃炎」という状態になりますが、除菌治療をしても一度萎縮した(薄くなった)胃の粘膜は元には戻りません。
除菌をした年齢が若ければ若いほど(20歳代に近いほど)、胃の粘膜は修復され内視鏡での見た胃の粘膜は修復され元通りに見えることがあります。しかし、ヘリコバクター・ピロリ菌による炎症は、胃粘膜細胞の遺伝子の傷を起し、その傷により胃がん細胞が発生します。除菌治療だけではこの遺伝子の傷までは修復できません。つまり一度萎縮した胃の粘膜からは経年変化の中で胃がんができやすい状態なので、将来に渡って胃がんが発生していないかどうかの注意が必要になります。
そのため除菌をした方は1年に1回は胃内視鏡検査を受けられることを強くお勧め致します。
除菌後にピロリ菌に再感染することはありますか?
1次除菌もしくは2次除菌を行い、治療判定として尿素呼気試験等で除菌成功をきちんと確認すれば、基本的に再感染することはないと考えられます。
1年後に再度ピロリ菌の検査(ほとんどが健診や人間ドックなどでの抗体検査)をすると、0~1%程度の方で陽性と判定されることがあります。ピロリ菌除菌により、体内からピロリ菌が除去された段階で、体内の免疫細胞がピロリ抗体を産生しなくなるので、一度産生された抗体は1~3年をかけて陰性化していきます。
ほとんどが、ピロリ抗体価が基準値以上(>10)まで低下していないための陽性判定例が多いと考えられます。例えば、除菌前のピロリ抗体化が100以上だった方が、健診などでのオプション項目でピロリ抗体が含まれていて1年後の抗体価が30と低下していたとしても、その1点だけを見れば抗体価は基準値以上なので陽性と判定されかねません。
ただし、再陽性例は少なからず存在し、その多くが除菌後にピロリ菌の菌量が著しく低下したが完全には菌を駆除できていなかった状態で、実は成功していないにも関わらず「陰性」と判定されたグレイゾーン(尿素呼気試験で2~2.4‰)で、その後、再びピロリ菌量が回復してきたために、再度「陽性」になったものと考えられています。
グレイゾーンであった場合は、翌年以降の胃内視鏡検査における胃粘膜の炎症が沈静化しているかどうかを含めて、ピロリ抗体の変化を追っていくか、再び尿呼気試験をして値を確認することが必要になります。
除菌後に胸やけを感じますがなぜですか?
除菌に成功した患者さんの中で、10%程度ですが胸焼けなどの胃酸逆流症状を感じることがあります。これは、除菌治療により炎症が沈静化しますが、ピロリ菌感染による炎症で低下していた胃液の分泌が正常に戻ったために、一時的に起こると考えられています。
除菌治療により胃の働きが正常化しているために、除菌前よりも食欲が戻る方も比較的多くいます。本来の胃の働きである胃酸分泌が正常化していると、以前よりも胃酸分泌が多くなる胃酸過多が起こり、結果的に胃酸逆流症状となるのです。
ただし除菌後に起こる胃酸逆流症状は一時的なもので、多くは軽症なので経過観察で良いのですが、症状が強い方は胃酸を抑える内服薬での治療を一時的に行えば軽快することほとんどです。
ペニシリンアレルギーですが除菌できますか?
ピロリ菌の除菌治療は基本的に2回目までが保険適応となりますが、使用する抗生剤には必ずペニシリンが含まれます。3回目の除菌治療である3次除菌からは保険適応がなく自費診療となりますが、ペニシリンを含まない抗生剤を選択する組み合わせが主流です。
ペニシリンアレルギーをお持ちの方は、保険診療でのピロリ菌除菌ができないと想定されます。この場合は、上記の通りペニシリンを含まない抗生剤を選択する必要がありますので、自費診療で行われる3次除菌と呼ばれる治療薬の組み合わせを用いることを考慮します。一般的には、胃酸分泌抑制剤としてボノプラザン(タケキャブ)、抗生剤としてメトロニダゾール(フラジール)、シタフロキサシン(グレースビット)を使用します。
最後に
今回はヘリコバクター・ピロリ菌に関するよくある質問についてまとめてみました。ピロリ菌に関する基礎知識、胃がん、ピロリ菌除菌後の注意などについて説明しました。ピロリ菌の感染によって慢性胃炎の変化が起こった結果萎縮性胃炎が生じますが、一度起きてしまった萎縮性胃炎からは早期胃がん発生のリスクが高いので注意が必要です。つまり、ピロリ菌除菌治療だけで胃がんの発生をゼロにすることは出来ませんし、胃がんの予防ができる訳ではないので、胃がんが発生していないかどうかを見るために、定期的に胃内視鏡検査を受けることが極めて重要になります。